
Excelのデータを利用することは多いです。他の方が作ったExcelデータを利用する機会も多いですが、Excelを使いこなしている方のデータを利用するといつもと表示が違う=トラブル?ということがあります。Excelのことで、簡単に回避=修正できることを解説します。
● トラブル事例 021: ファイルを開いたら表示が違う!?
エクセルファイルを開いてみたら、表示が違う。いつもある目盛線がなかったり、みたこともない表示で表以外がグレーになっている、いつも自分が使っているエクセルの表示と違っている、どうすれば良いかわからない。
対応方法
● 表以外がグレー
原因: 表示を「改ページプレビュー」に切り替えているからです。
対応方法: 「表示」タブ → 「標準」ボタンをクリックすると、改ページプレビューから標準に変わりグレー表示が解除されます。
● 目盛線がない
原因: 印刷の仕上がりを画面で確認するため、セルを区切っている目盛線が消えて表示している。
対応方法: 「表示」タブで目盛線(枠線)にチェックを入れると、目盛線(枠線)が表示されます。
● 数式バーや列番号・行番号がない
原因: 表示を消している
対応方法: 「表示」タブ → 「数式バー」と「見出し」にチェックを入れると、数式バーと列番号・行番号が表示されます。
〈 Excelのシュートカットキー 〉
マウス右クリックから「コピー」「貼り付け」をCtrl+CやCtrl+V で作業完了
覚えれば、業務効率が大幅にアップします。
- Ctrl+C: 選択したセルをコピー
- Ctrl+X: 選択したセルを切り取り
- Ctrl+V: コピーしたセルの内容を任意のセルに貼り付け
- Ctrl+S: 上書き保存
- Ctrl+Z: 直前の作業を1つ元に戻す
- Ctrl+P: 印刷プレビュー画面を開く
- Ctrl+Alt+V: 形式を選択して貼り付け
- Ctrl+1: セルの書式設定ダイアログボックスを表示
- Ctrl+Shift+L: フィルターを設定する・解除するく
- Ctrl+カーソルキー: 連続データの末尾に移動する
- Ctrl+Shift+カーソルキー: 連続データの末尾まで選択する
- Ctrl+W: アクティブブックを閉じる
Excelのトラブル等についてもお気軽に福島リコピーへご相談ください。

2025年10月に、Windows10 はサポートを終了します。新しいパソコンの導入を検討しはじめる方もいらっしゃるのではないでしょうか。Windows8 のパソコンを、Windows10にOSを変えて、パソコンのスペックの問題で立ち上がりが遅くなってしまっているという話も聞きます。Windows10 を利用している方から Windows11 にしようと思うけど、どうですか?とご相談を受けて、パソコンを確認しましたところ、メモリーが4GBしかないパソコンでした。Windows11 を利用するなら、パソコンを購入することをご提案しました。新しいパソコンへの準備や設定についてご説明します。
現在ご利用中のパソコンが故障している場合は、作業内容が変わります。
以下の内容は、現在利用しているパソコンが問題なく稼働していることを前提です。
パソコンの買い替え時に行うべきこと
1: 現在利用しているパソコンからのデータをバックアップ
パソコンからバックアップするときは、バックアップしたい容量を必ず確認してください。
バックアップするストレージの仕様も注意が必要です。買ったけれど使えないこともあります。
2: いろいろなログイン情報の取得
ログイン情報をパソコンに覚えさせておいたまま、新しいパソコンでログインできない、結構ある話です。
3: メールデータの移行作業準備
メールアカウント情報をしっかりメモしてください。
メールソフトを利用しているうちに、導入初期にいただいたメール設定情報が変わっていたという話もあります。
〈 アドレス帳のデータ 〉
新しいパソコンで送信しようとしたら、いつも出るメールアドレスが出ない!とご相談もあります。
〈 送/受信データ 〉
不要でしたら移行作業はありませんが、あの時のメールが見たい。そこが不安で、新らしいパソコンの横に古いパソコンを置いておくのをたまに見ます。
4: インターネット接続情報
設定が必要な場合と何も設定しない場合があります。社内の環境によってことなります。
5: 周辺機器の接続情報
古いインクジェットで新しいOSはサポートしていない場合もあります。
新しいパソコン利用開始時に行うべきこと
- インターネット接続
- 新しいパソコンの起動を行い、各種初期設定
- バックアップデータの移行
- メールソフトの設定とバックアップデータの移行
- 周辺機器の設定
- 新しいOSで操作方法が変わりますので覚える
古いパソコンの処分
ハードディスクを初期化しても、専門的知識のある人に渡れば、データを復旧させてしまいます。また、ゴミとして廃棄することもできません。古いパソコンの処分は安心できる専門業者を利用することをお勧めします。
上記作業は、バックアップやインストールの失敗をしないことを前提に説明しています。
パソコンの初期設定、OSやオフィス系のトラブル、パソコンの故障など心配がある場合、総合的なサポートの「PCパック」をご利用ください。
PCパックはデータ復旧サービスやマルウェア対策までカバーできます。早急にご対応が可能です。故障した時やITマネージメントサービス→PCの障害切り分けができます。
● PCパックの詳細についてチラシを見る
パソコンの入替のご相談や「PCパック」についての詳しい内容の説明
福島リコピーへお気軽にご連絡ください。

お客さまや取引先に対して「待っています」ということを、より丁寧に伝えたいときに「お待ちしております」というフレーズを使うことがあります。打ち合わせやイベントがおこなわれるとき、メールや電話にて頻繁に使う表現でもあり、使う場面が多いからこそ正しく使えるよう、意味や使い方、例文や言い換え表現、注意点について解説いたします。
「お待ちしております」の意味
「お待ちしております」は「待っています」を丁寧に表現した言葉です。接頭語の「お」をつけたり、「おります」という謙譲表現にすることで、相手に対する敬意を示す言葉です。
「待つ」の言葉には、 物事・人・時が来るのを予期し、願い望みながら、それまでの時間を過ごすという意味があります。「お待ちしております」には、待っているだけでなく「望んでいる」「期待している」という意味も含まれます。
「ご来店をお待ちしております」や「ご連絡をお待ちしております」など、話し言葉としても書き言葉としても、お客さまや取引先に対してさまざまなシーンで使用可能です。
「お待ちしております」の使い方と例文
さまざまなビジネスシーンで活用できる「お待ちしております」の、使い方と例文を紹介します。
注意点なども併せて確認いただき、状況や相手に応じて言葉を使い分けましょう。
1: ご連絡(ご返信/ご返答)をお待ちしております
「ご連絡をお待ちしております」は、何か聞きたいことがある場合や確認してもらいたいとき、相手からの返信・返答が必要な場面で使うことが多いです。「ご連絡ください」よりも「お待ちしております」の方がやわらかい印象になります。なお、連絡や返事の期日を設けている場合は、その旨を伝えるようにしましょう。
使い方の例文は、下記のとおりです。
〈 例文: ご連絡(ご返信/ご返答)をお待ちしております 〉
▢ 会議の日程調整につきまして、ご連絡をお待ちしております。
▢ プロジェクトの進捗状況について、ご連絡をお待ちしております。
▢ 製品の配送スケジュール、ご連絡をお待ちしております。
2: お待ちしておりますので~
「お待ちしております」と言い切ると、少し厳しい印象で気になるという場合は、「お待ちしておりますので~」を使うと柔らかく伝えられます。
状況や相手との関係性で使い分けるとよいでしょう。
使い方の例文は、下記のとおりです。
〈 例文: お待ちしておりますので~ 〉
▢ ご連絡をお待ちしておりますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
▢ 折り返しのご連絡をお待ちしておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
▢ ご来場をお待ちしておりますので、ぜひお時間をお作りいただけますと幸いです。
3: お待ち申し上げております
目上の人に対して、より丁寧な表現で伝えたいときは「お待ち申し上げております」を使います。謙譲語が2つ続く二重敬語ともいわれていますが、社会に浸透している言葉でビジネスシーンでも使うことが可能です。敬意の強い表現で堅苦しい印象を与えるため、どちらかというと口頭よりも文書やメールを中心に使用されています。
使い方の例文は、下記のとおりです。
〈 例文: お待ち申し上げております 〉
▢ ご連絡をお待ち申し上げております。
▢ 社員一同、皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げております。
▢ 〇〇様のご来訪をお待ち申し上げております。お会いできることを楽しみにしております。
「お待ちいたしております」と「お待ちしてます」は誤った言葉?
「お待ちいたしております」と「お待ちしてます」について、注意点を紹介します。
● お待ちいたしております
より丁寧に伝えようと「お待ちいたしております」としてしまうのは二重敬語となります。「する」の謙譲語「いたす」と、「いる」の謙譲語「おります」は両方とも謙譲語です。同じ敬語表現を重ねて使う「お待ちいたしております」は使わないようにしましょう。
● お待ちしてます
本来入るべき「い」が省かれた表現を、「い」抜き表現といいます。くだけた印象になるため、ビジネスシーンで使うのは避けましょう。意味は伝わりますが「お待ちしています」と丁寧な表現で伝えるようにしましょう。
「お待ちしております」の言い換え表現
「お待ちしております」を言い換える場合、「お越しください」や「よろしくお願いいたします」の表現が使えます。それぞれ言葉の持つニュアンスは異なります。言葉の前後や状況に合わせて使い分けるのがよいでしょう。
1: お越しください
「お越しになる」は「来る」の尊敬語です。「お越しください」は「来てください」を丁寧に表現した言葉です。相手が自分のところに来るのを待つ場合のみに使用します。同僚や部下、後輩には使わず、お客さまや取引先など、目上の人に丁寧に伝えたい場面で使います。
使い方の例文は、下記のとおりです。
〈 例文: お越しください 〉
▢ 〇月〇日、〇時にお越しください。
▢ 〇月△日に弊社で発表会を行いますので、ぜひお越しください。
▢ お待たせする場合もございますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
2: よろしくお願いいたします
「よろしくお願いいたします」は、相手に依頼をするときに添える敬語表現です。なるべく短く伝えたい場合に使います。相手にとって「お待ちしております」がプレッシャーになりそうなときは「よろしくお願いいたします」を使うといいでしょう。
使い方の例文は、下記のとおりです。
〈 例文: よろしくお願いいたします 〉
▢ ご連絡のほどよろしくお願いいたします。
□ 〇月△日までにお返事をいただけますよう、よろしくお願いいたします。
□ 〇時までに会議室前によろしくお願いいたします。
「お待ちしております」への返事の仕方
相手から「お待ちしています」と言われたとき、状況に応じて適切な返事をすることが重要です。
「ありがとうございます」や「かしこまりました」、「承知いたしました」などのあらたまった表現や、「わかりました」などを使い分けましょう。「よろしくお願いいたします」でもかまいません。
イベントの案内などの文書に返事をするときはお礼の言葉を伝え、「当日を楽しみにしております」など楽しみにする自分の気持ちも添えるとよいでしょう。
「お待ちしております」の意味や使い方、例文や言い換え表現、注意点について解説しました。「お待ちしております」は、対面の会話のほかにもメールや電話などビジネスシーンで頻繁に使われる表現でもあります。相手や状況に応じて言葉の意味合いを理解し、状況にあった敬語の言い換え表現を使い分けて、円滑なコミュニケーションがとれるように心がけましょう。
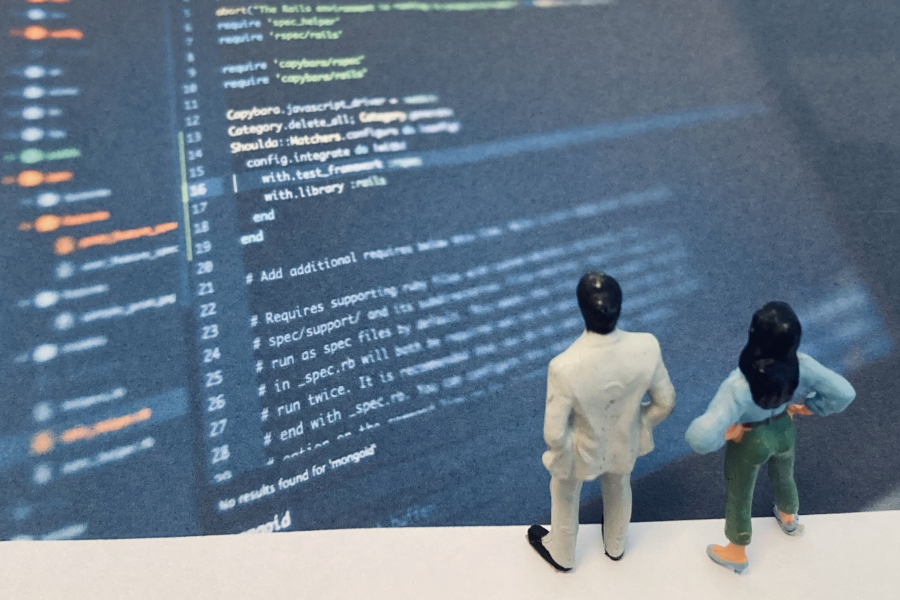
オフコン(オフィスコンピューター)や、メインフレームをご存じでしょうか。メインフレームと呼ばれる大型コンピューターやオフコンという事務処理に特化した大型でないコンピューターです。そのコンピューターは今でも現役で活躍していますが、導入から長期間経過し、現代のシステムとの融合ができないものがほとんどです。システムのベースや技術は古いままであるため、いろいろな問題は生じてしまいます。
レガシーシステムとは
レガシー(Legacy)は、遺産、伝統などの意味があります。過去の技術で構築されている古いシステムのことをいいます。システム開発から、20年以上経過している場合もあり、基幹システムとして利用されていることが多いです。
〈 レガシーシステムの問題点 〉
□ 大規模なシステム障害のリスク: 古い技術基盤のため、新しいシステムとの統合が難しく、障害が発生しやすい。
□ 保守・管理コストの増加: 老朽化に伴い、メンテナンス費用や専門人材の確保が必要。
□ セキュリティの脆弱化: 最新のセキュリティ要件に対応できず、サイバー攻撃のリスクが高まる。
□ 属人化の進行: 特定の担当者しかシステムを理解・操作できない状態に陥りやすい。
□ 競争力の低下: 新しい技術を取り入れられず、ビジネスの競争力が低下する可能性がある。
レガシーシステムからの脱却方法
レガシーシステムの問題を解決するためには、現状のシステムをしっかりと把握し、適切な移行計画を立てることが重要です。これにより、最新の技術を取り入れ、ビジネスの競争力を維持・向上させることができます。
● モダナイゼーション
老朽化した既存のコンピューターシステム(レガシーシステム)を、現在のニーズに合わせたシステムへ変えることです。たとえば、データなどのリソースを生かしたまま、システムなどを、最新技術を利用したものへと置き換えることです。
● マイグレーション
既存システムやソフトウェア、データなどを別の環境に移転したり、新しい環境に移行することです。
2025年10月に「Windows10」のサポートが終了します。
「Windows10」から「Windows11」への転換をご検討ください。
Q: 「Windows10」から「Windows11」への転換する利点は?
A: 新機能の搭載や性能アップにより使用感・効率が向上している。機能の改善により使いやすくなっています。
Q: 「Windows11」を利用するのにどのようなPCが望ましいか。
A: 弊社営業がお使いのPCの要件等を確認し、お客さまの使用環境等にあった商品を選定します。
レガシーシステムや、最適な利用環境については、福島リコピーへ是非ご相談ください。

2025年は「2025年問題」や「2025年の崖」というキーワードが出てきます。「2025年問題」という超高齢化社会になり、働き手不足や社会保障費の急増などが見込まれる社会問題です。また、デジタル化の遅れが招く経済的リスクから「2025年の崖」という問題にも直面します。
2025年問題とは
日本人の5人に1人が75歳以上となり、後期高齢者が大幅に増えることで、社会に大きな影響を及ぼす問題となります。
人材不足も加速する状況になります。
〈 2025年問題の課題 〉
1. 社会保障費の増加
□ 高齢者の増加に伴い、医療費や介護費用が急増し、社会保障費が大幅に増加する。
□ 現役世代の負担が増え、経済的な圧力が強まる。
2. 医療・介護体制の維持
□ 医療・介護サービスを支える人材が不足し、サービスの質の低下や地域格差が拡大するリスクがある。
3. 労働力不足
□ 高齢化により労働力人口が減少し、経済成長が鈍化する恐れがある。
4. 中小企業の後継者不足
□ 多くの中小企業で後継者が見つからず、廃業が増加する可能性がある。
2025年の崖とは
2018年に経済産業省が発表した “DXレポート~ITシステム「2025年の崖」” では、日本企業のシステムの問題解決や、経営改革がおこなわれなかった場合、2025年以降に最大12兆円/年の経済損失が生じるといわれています。
DXを推進できず国際競争力を失う問題を指しており、警鐘を鳴らす意味を込めて「2025年の崖」と呼びました。
〈 2025年崖の問題 〉
□ 既存システムの機能が複雑化・ブラックボックス化している。
□ 既存システムに関する問題解決も含め、業務自体の見直し(経営改革)も求められる中、新システムへの業務見直しに現場からの反発によってDXが妨げられている。
たとえば事業部ごとに異なるシステムが構築されていたり、カスタマイズされているケースが多く、事業部間の情報共有や連携不足により、新システム移行が容易ではない。
2025年問題と壁への対応策
IT導入補助金を使用し、企業の生産性向上に繋がる「ITツールの導入」を検討する
中小企業庁チラシ: https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_it.pdf
● ITツール導入の一例
□ 介護、医療現場支援ソフト「ほのぼのシリーズ」
NDソフトウェア株式会社は、介護・福祉・医療分野に特化した業務支援システムを提供する企業です。主力製品である「ほのぼの」シリーズは、介護事業者向けの「ほのぼのNEXT」や障がい福祉事業者向けの「ほのぼのmore」など、多様なニーズに対応しています。
〈 主な製品・サービス 〉 https://www.ndsoft.jp/product/
- ほのぼのNEXT
介護事業者向けの業務支援システムで、業界トップクラスのシェアを誇ります。利用者のケアプラン作成や請求業務の効率化を支援します。 - ほのぼのmore
障がい福祉事業者向けのシステムで、障がい者総合支援法に対応し業務全般をサポートします。 - Care Palette
訪問系事業所向けのアプリで、簡単かつ便利に記録を行うことができます。 - AIケアプラン
介護保険対応のケアプラン作成を支援するシステムです。 - Voice fun
音声入力支援システムで、介護福祉用語に特化しています。 - ほのぼのIoTクラウド
IoT機器からの情報を取り込み、システムと連携させることで業務の効率化を図ります。
「2025年問題」と「2025年の壁」への対応策について、ご不安なことやわからないことは、お気軽に福島リコピーへご相談ください。
福島リコピーフェア2025 開催決定!!
2025年 2月5日(水) 会津会場 / 2月7日(金) 福島会場 の2Days開催となります。
詳細は下記をご確認ください。ダウンロードボタンより、資料のダウンロードが可能です。

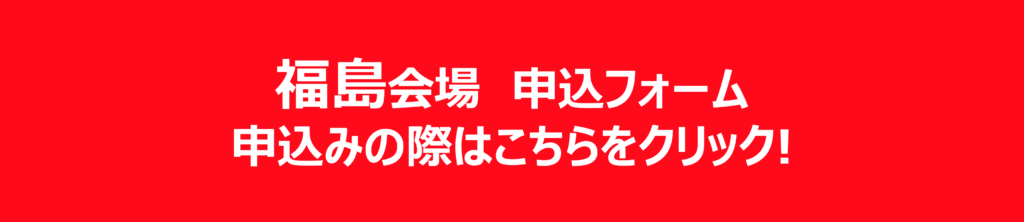
2025年1月22日 更新

ビジネスメールで仕事の用件のほかに相手の体調を気遣うケースがあります。ビジネスのコミュニケーションにおいて、相手の体調を気遣うことは、信頼関係を築く上で重要です。具体的にどのような内容を記載すればよいのでしょうか。相手の体調を気遣うメールの言葉の選び方・注意点について解説いたします。
体調を気遣うメールを送るシチュエーション
ビジネスにおいて相手の体調を気遣うメールが必要な場面は、大きく分けて2つがあります。
● 仕事で関わりのある相手が、体調を崩した場合
● 季節の変わり目などに、気遣いとして送る場合
仕事関係の相手が体調を崩したことを知ったとき、体調不良による欠勤・欠席の連絡を受けたとき、一定期間の病気療養が必要な場合や、季節の変わり目や感染症の流行時に相手を気遣う場合などに、体調を気遣うメールを送るケースがあります。状況に合わせた相手を思う気遣いの言葉をメールで送ることは、信頼関係の構築や良好なビジネス関係の維持にもつながります。
相手の体調を気遣う言葉
体調を気遣うメールで使う言葉は、さまざまなものがあります。
それぞれの意味と使い方を紹介します。状況や相手に応じて言葉を使い分けましょう。
1: ご自愛ください
「ご自愛ください」は、「体調を崩さないように気をつけてください」や「ご自身のお体を大切にしてください」という、相手の健康を気遣う意味が込められた言葉です。相手の体調に対する気遣いを表す言葉として、取引先や上司など、目上の人に対しても、問題なく使える表現のひとつです。
注意点としては、「体調を崩さないように気をつけてください」という意味から、すでに体調の悪い人に対して使うのは不適切とされています。また「ご自愛」という言葉に「ご自身のお体を大切にしてください」という意味が含まれていることから「お体を、ご自愛ください」、「体調に気をつけて、ご自愛ください」という表現にしてしまうと、同じ意味を重ねている二重表現となり好ましくありません。
「ご自愛ください」は、ビジネスシーンで使いやすい表現のひとつですが、使う状況や相手に注意が必要です。「ご自愛ください」のみで正しい表現ですが、目上の人に対しては「どうぞ」や「くれぐれも」、「何卒」などの言葉を添えると、より丁寧さが伝わります。
使い方の例文は、下記のとおりです。
〈 例文: ご自愛ください 〉
▢ 厳しい寒さが続いておりますので、くれぐれもご自愛ください
▢ 本年も健康で素敵な日々が続きますよう、どうぞご自愛ください
▢ 風邪など召されませぬよう何卒ご自愛ください
2: お体に気を付けてお過ごしください
「お体に気を付けてお過ごしください」も、相手の健康を気遣う表現として目上や目下にかかわらず幅広く使える言葉です。
より丁寧な表現にする場合は「気を付けて」の前にも「お」を付けて、「お体にお気を付けてお過ごしください」としたり、「どうぞ」「くれぐれも」などの言葉を付け加えて「どうぞ、お体にお気を付けてお過ごしください」とするといいでしょう。
すでに相手が体調を崩している場合に「体に気を付けて」という意味の言葉を使うと、失礼にあたりますので注意しましょう。また「お体」と「お身体」、どちらを使うか悩む方もいらっしゃいますが、「体」は頭から足全体の肉体を表す意味があり、「身体」には心も含む人の体の意味があります。どちらを使っても間違いではありませんが、法律や報道など公的な文書では「体」が使われます。基本的には「体」の方を使うことが多いようです。
使い方の例文は、下記のとおりです。
〈 例文: お体に気を付けてお過ごしください 〉
▢ 季節の変わり目でございますので、どうぞお体にはお気をつけてお過ごしください
▢ ご無理をなさいませんよう、お体に気をつけてください
▢ ご多用とは存じますが、くれぐれもお体に気を付けてお過ごしください
3: お大事になさってください
「お大事になさってください」は、病気や怪我をしてしまった相手に対して使う気遣いの言葉です。
目上の人には「お大事に」や「お大事にしてください」という表現は使わずに「お大事になさってください」を使います。また「どうぞ」や「くれぐれも」などの言葉を添えると、より丁寧さが伝わります。「お大事になさってください」は、「体を大切にする」という意味を含んでいるため「お体を、お大事になさってください」は、不適切な表現となりますので注意しましょう。
使い方の例文は、下記のとおりです。
〈 例文: お大事になさってください 〉
▢ 寒い日が続きますが、くれぐれもお大事になさってください
▢ 入院されていると聞きました。ご無理なさらず、お大事になさってください
▢ 1日も早いご回復をお祈りしております。 どうぞお大事になさってください
4: お見舞い申し上げます
一時的な体調不良ではなく、病気や怪我による入院などの長期的な療養や、事故や災害に遭った人に「お見舞い申し上げます」という表現を用いて、気遣いの気持ちを伝えることができます。立場や年齢など関係なく使えます。お見舞いの気持ちを強調したい場合には、「心より」や「謹んで」を加えましょう。具体的な理由を添えて相手への気遣いを示しましょう。
使い方の例文は、下記のとおりです。
〈 例文: お願いいたします 〉
▢ ご入院されると伺いました。謹んでお見舞い申し上げます
▢ 通勤途中の思いもかけぬご災難、心よりお見舞い申し上げます
▢ ○○○の被害を知り、謹んでお見舞い申し上げます
相手の体調を気遣う際の注意点
相手の体調を気遣うメールを送る際の注意点を解説します。言葉選びを誤ると相手に不安や不快感を与えてしまう恐れがあります。適切な言葉を選び簡潔にまとめるのがポイントです。相手を気遣うあまり、メールが長くなってしまわないよう注意しましょう。
● 忌み言葉は避ける
忌み言葉とは、不吉なことを連想させるため使用を控えたほうがよいとされている言葉のことをいいます。相手が不快にならないよう、体調を気遣うメールでは、痛み・苦しみ・終わり・消滅などを連想させる言葉や、繰り返すことや長引くことを連想させる言葉、「四」や「九」という数字は使わないようにしましょう。
苦痛を連想させる言葉: 痛い / 苦しい / 悲しい / 辛い / 病む など
終わりを連想させる言葉: 終わる / 滅びる / 消える / 絶える / 壊れる など
繰り返すことや長引くことを連想させる言葉: たびたび / 次々 / 続く / 長い / 再度 / またまた / 繰り返す / 重なる / 重ねて / 重ね重ね / しばしば / いよいよ / いろいろ / 返す返す など
● プレッシャーを与える言葉は避ける
体調を気遣うメールを送る際は、相手にプレッシャーがかかる言葉は避けるようにしましょう。具体的な症状や病名を尋ねたり、「頑張ってください」や「1日も早く」、「お待ちしています」など復帰を急かしたりするフレーズは避け、相手が療養や治療に専念できるようにしましょう。
返信を急がないメールや、返信が不要なメールの場合は「返信不要です」や「ご返信はお気遣いなく」、「ご返信には及びません」や「ご返信は急ぎません」などの言葉をメールに添えることで、相手に負担をかけずに済むでしょう。
療養や治療に専念してもらえるように「どうぞ治療に専念されて、順調にご回復されますようお祈りいたします」など配慮の言葉もあるとよいでしょう。悪気がなくても復帰を急がせていると受け取られてしまうことがありますので、相手の立場になって思いやりのある言葉選びをしましょう。
相手の体調を気遣うメールの言葉の選び方・注意点について解説しました。体調を気遣うメールは、OKの言葉遣いとNGの言葉遣いがあります。相手に寄り添った表現にすることを意識して、良好な関係を築いていきましょう。

年末年始休暇等の長期休暇明けのパソコンでのメール受信は、場合によってはとても危険な状況になっています。悪意のあるメールを受信して、そのメールを開いたことで大変なことになることは他人ごとではありません。連休明けのメールトラブルに合わないための方法について解説します。
● トラブル事例 020: 長期休暇明けに起こり得るメールトラブル!?
連休明けのメールチェック。もしかすると大量の受信したメールの中に、悪意ある人たちからの攻撃メールが潜んでいるかもしれません。メールトラブルを少しでも対処したいけどどうすれば良いかわからない。
対応方法
● メールを受信する前にパソコンの準備を行う
OSや各種プログラムの更新プログラムが終わっていますか。更新プログラムの有無を確認し、更新が必要な場合はメール受信の前に作業完了をしてください。場合によっては、長期休暇中に利用しているシステムのセキュリティホールが発見されて更新プログラムが配布されている場合もあります。
● 受信しているメールをいつも以上に気を付ける
不審なメールは「添付ファイルは開かない」「本文中のURLにはアクセスしてはいけない」が基本です。取引ある会社名でも送信メールアドレスがいつもと違う場合は、送信元に連絡し確認し問題ないと認識できるまで受信メールは開かないが鉄則です。なりすましメールとは、悪意のある第三者が実在する企業や団体を装って送信する電子メールです。長期休み明けは、特に危険ですので十分に気を付けてメールを確認ください。
悪意のあるメールや危なそうなメールを開いてしまった時は、そのパソコンのインターネットを遮断し、福島リコピーへご相談ください。 インターネットを切ることで、他のパソコンへの影響は少なくなります。

年始休み中の1月1日に、M7.6を観測した能登半島地震や連休中の災害が多かった2024年です。地震や豪雨災害による会社の社屋内の被害として、パソコンや電子機器が使えないような状態になっているのを、テレビニュースで見ることもあります。
多くの企業業務はパソコンを利用していることから、災害でデータにアクセスできなくなった場合、業務が回らないようなことにならないことが考えられるため対策が必要です。災害でどのようなことがあるのかを理解し、どういう対策が必要になるかについて説明します。
自然災害での被害例
〈 地震 〉
地震を予測はできない分、日ごろからの対策は必要です。地震による影響は広範囲になり、インフラの復旧にもかなりの時間が必要です。
● 建物の倒壊により事務所に入れない
● 電子機器の転倒やモノがぶつかり破損して利用できない
● インフラが不通でなにもできない
〈 豪雨などの風水害 〉
豪雨などは、事前に天気予報で対策もできますが、予想をはるかに超えた被害が多くなっています。
● 床上浸水による電子機器の故障
● 水害の状況により建物自体の破損
● 水害による社内物品の流出
データの保全
電子機器の被害より深刻なのが貴重なデータを守ることです。企業の大部分は、データ保管をNASなどで社内に保管している場合が多いです。
社内=自然災害への対応としては、万全ではないので、NAS + オンラインストレージをバックアップとして利用することをおすすめします。
オンラインストレージ「RICOH Drive」は、現場・オフィス・ホームをつなげて、社内・社外のファイル共有を安全・簡単におこなうことで、企業のデジタル化を支援します。「RICOH Drive」については、以下のページで確認いただけます。
オンラインストレージ RICOH Drive: https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-drive
企業に求められるBCP対策
福島リコピーでは、BCP(事業継続計画)点検シートをもとに、お客さまの問題点解決のお手伝いを行っております。
オンラインストレージやBPC対策は、福島リコピーへお気軽にご相談ください。
2024年12月16日
福島リコピー株式会社
毎度格別の御引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では誠に勝手ながら下記の日程につきまして、年末年始休業とさせていただきます。
つきましては、何かとご不便をお掛けすることと存じますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
休業期間のご案内
2024年 12 月 28 日(土) 休業
2024年 12 月 29 日(日) 休業
2024年 12 月 30 日(月) 休業
2024年 12 月 31 日(火) 休業
2025年 1 月 1 日(水) 休業
2025年 1 月 2 日(木) 休業
2025年 1 月 3 日(金) 休業
2025年 1 月 4 日(土) 休業
2025年 1 月 5 日(日) 休業
2025年 1 月 6 日(月) 営業(弊社年末業務処理の為、15:00 までの営業となります。)
※ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2025年 1 月 7日(火)より通常営業となります。
【故障・修理のお問い合わせについて】
リコー製品の故障・修理につきましては、年末年始休業期間中は下記のとおり受付しております。
12 月30 日(月)9:00~17:30受付(標準訪問時間:9:00~17:00)
お電話での受付:0 1 2 0 – 8 9 2 – 1 1 1
- 17:00以降の受付は、原則翌営業日の修理となります。
- 道路混雑等により、修理対応までにお時間のかかる場合がございます。
- 修理受付ダイヤルは、お問い合わせの集中により、電話がつながりにくい事象が発生する場合がございます。特に年始の営業初日は大変混み合いますので、その場合は誠にお手数ですが、Web、チャットボット、複合機本体からの修理依頼方法もご利用いただけますようお願いいたします。
お問い合わせは、お電話以外の方法でもお受けしております。
下記リンクの「故障・修理のお問い合わせについて」から、別の方法でもご対応いただけます。
【消耗品等のご注文・お届けについて】
2025年 年末年始休業期間中の商品のご注文、お届け、およびお問い合わせ窓口について、下記にてご案内申し上げます。
年末年始期間中につきましては、物流増加にともない、
商品のお届けに遅れが発生する場合も予想されますので、余裕をもってのご注文をお願いいたします。
※この期間中、お問い合わせにつきましては誠に申し訳ございませんが、対応ができかねます。
ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。
また、NetRICOHを利用した、休業期間中の注文に関しては下記リンクからご確認ください。
【 NetRICOH ログインページ 】
